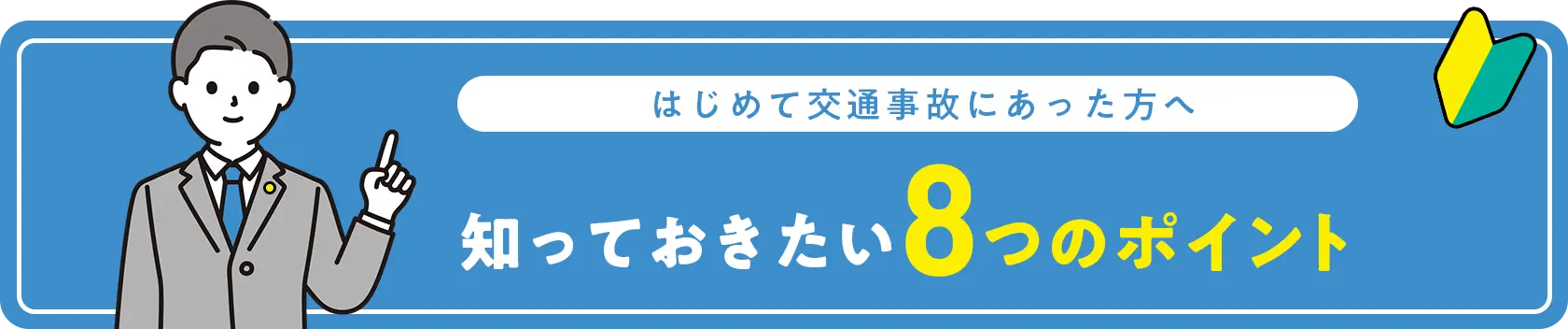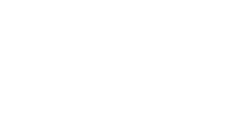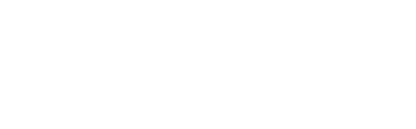人身事故と物損事故とは
交通事故は、死傷者が出た「人身事故(人損事故)」と、ケガ人が出ずに自動車や建物等の損壊で済んだ「物損事故(物件事故)」に分かれます。交通事故が人身事故か物損事故かは、警察が現場検証を行なって判断します。
なお、事故当初は、身体に異常がなかったため物損事故となったものの、後日体調が悪くなったり、痛みが出てきたりした場合には物損事故から人身事故に切り替えることが可能です。
人身事故の場合、自動車賠償責任法が適用され、自賠責保険に損害賠償請求を行なうことができ、傷害の場合で120万円を限度に損害の賠償を受けられますが、物損事故には自動車賠償責任法が適用されないため、自賠責保険に損害賠償請求を行なうことができません。そのため、事故当初、身体に不調がなかったために物損事故としたものの、後日体調が悪くなったり、痛みが出てきたりした場合、自賠責保険から補償を受けるためには、人身事故の事故証明書が必要なため、物損事故から人身事故に切り替える必要があります。
人身事故へ切り替えるには、医師に診断書を書いてもらい、警察に提出する必要があります。また、被害者と加害者がともに警察に出向いたうえで、再度、事故現場で実況見分に立ち会うことになります。事故から日数が経過していると、「体調不良と事故の関連性が不明」とされて、切り替えができないことがありますので、切り替えを希望する場合は、早めに警察に届け出ましょう。
※その他、人身事故と物損事故の違い
人身事故は、刑事処分(懲役、罰金、禁錮など)、行政処分(免許停止、免許取消)の対象になりますが、物損事故は、基本的には刑事処分や行政処分の対象になりません。
人身事故における3つの損害
人身事故とは、人の生命・身体に対する侵害を伴う事故のことです。
人身事故によって生じる損害は、財産的損害である「積極損害」、「消極損害」、精神的損害である「慰謝料」の3種類に分かれます。
人身事故における損害賠償を請求できる相手
交通事故の被害にあった場合、損害賠償は、加害者(運転者)はもちろんのこと、加害車両の運行供用者(所有者等)や、加害者の使用者(雇用主、会社等)にも請求が可能なケースがあります。
加害車両の運転者だけでなく、所有者等も運行供用者として損害賠償責任を負う
自動車損害賠償保障法(自賠責法)第3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する席に任ず」とあり、加害車両の運転者だけでなく、所有者等も運行供用者として損害賠償責任を負うとされています。これを運行供用者責任といいます。
民法上の不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)では、被害者側が、加害者側の故意・過失を立証する必要がありますが、運行供用者責任では、被害者側は「自動車の運行によって人身事故が発生したこと」のみを立証すれば足りるため、被害者側からの責任追及が容易となっています。
一方、運行供用者は「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」、「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと」、「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと」の3つ全てを立証しない限り、損害賠償責任を免れません。
業務中だった場合には、その雇用主(会社)も使用者として損害賠償責任を負う
民法第715条では、「事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とあり、加害者が被用者(会社員)で業務中だった場合には、その雇用主(会社)も使用者として損害賠償責任を負うとされています。これを使用者責任といいます。
使用者は必ずしも雇用主とは限らず、「使用者に代わって事業を監督する者」も使用者と同等に損害賠償責任を負うとされています。使用者責任の場合では、被害者側による加害者(被用者)の故意・過失、加害者と使用者の使用関係、加害行為が使用者の事業の執行について行なわれたことの立証が必要になります。
また、使用者側には「使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」は、使用者の責任を免責するとされています。ただし、実際には、使用者の免責を認めることはほとんどありません。
物損事故における損害
物件事故(物損事故)とは、人の生命・身体に対する侵害はなく、車両や建造物などの物的な財産に対する侵害を伴う事故のことです。
財産的損害の賠償(修理費用等)のみが認められることが一般的で、原則として精神的損害賠償は認められません。また、自賠責保険の対象外です。
物損事故における具体的な損害の例
- 修理費
- 買替差額
- 登録手続関係費
- 評価損(事故歴による商品価値の下落)
- 代車使用料
- 休車損(営業車の場合)
- 雑費(レッカー代等)
- 営業損害等
- 積荷その他の損害
- ペットに関する損害
-
電話で申し込む
0120-316-279通話無料 平日 9:30-18:30 -
Webから申し込む
24時間受付
交通事故の損害
-
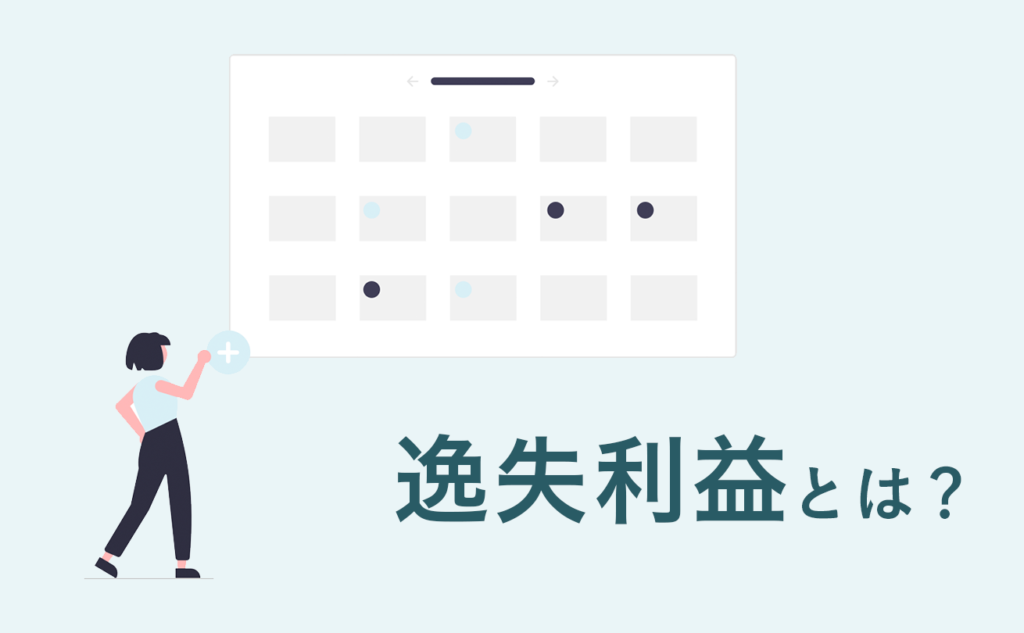 逸失利益とは?計算方法と増額のための5つのポイント【計算例あり】逸失利益とは、交通事故の被害に遭って障害が残ったり、死亡したりしなければ、将来的に得られるはずだった利益のことをいいます。逸失利益の計算方法と請求時に押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。
逸失利益とは?計算方法と増額のための5つのポイント【計算例あり】逸失利益とは、交通事故の被害に遭って障害が残ったり、死亡したりしなければ、将来的に得られるはずだった利益のことをいいます。逸失利益の計算方法と請求時に押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。 -
 損害の算定基準の違い人身事故において、損害額を算定するのに一定の基準があり、その基準に基づいて算定されます。損害の算定基準の違いについて詳しく解説しています。
損害の算定基準の違い人身事故において、損害額を算定するのに一定の基準があり、その基準に基づいて算定されます。損害の算定基準の違いについて詳しく解説しています。 -
 家事従事者(主婦・主夫)の休業損害家事従事者とは、家族のために家庭で料理や洗濯などの家事労働に従事する者という意味で、性別・年齢は関係なく主婦(主夫)などを指します。家事従事者(主婦・主夫)の休業損害ついて詳しく解説しています。
家事従事者(主婦・主夫)の休業損害家事従事者とは、家族のために家庭で料理や洗濯などの家事労働に従事する者という意味で、性別・年齢は関係なく主婦(主夫)などを指します。家事従事者(主婦・主夫)の休業損害ついて詳しく解説しています。 -
 休業損害について休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休んだために減った収入をいい、その補償を加害者側に請求します。休業損害について、弁護士が詳しく解説いたします。
休業損害について休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休んだために減った収入をいい、その補償を加害者側に請求します。休業損害について、弁護士が詳しく解説いたします。 -
 人身事故と物損事故交通事故は、死傷者が出た「人身事故(人損事故)」と、ケガ人が出ずに自動車や建物等の損壊で済んだ「物損事故(物件事故)」に分かれます。人身事故と物損事故の違いについてご説明します。
人身事故と物損事故交通事故は、死傷者が出た「人身事故(人損事故)」と、ケガ人が出ずに自動車や建物等の損壊で済んだ「物損事故(物件事故)」に分かれます。人身事故と物損事故の違いについてご説明します。 -
 治療・入通院等に関する損害積極損害とは、治療費や通院交通費のように、交通事故に遭ったことによって支出する必要が生じた財産的損害のことです。治療・入通院等に関する損害について解説します。
治療・入通院等に関する損害積極損害とは、治療費や通院交通費のように、交通事故に遭ったことによって支出する必要が生じた財産的損害のことです。治療・入通院等に関する損害について解説します。